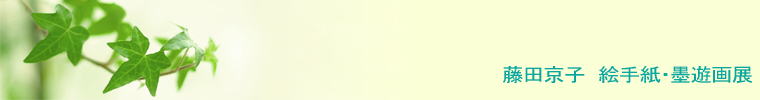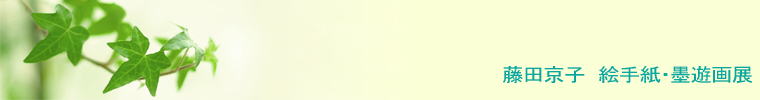<写真をクリックするとPDF版がダウンロードできます。>
1904年、ご主人と子供を中国に残したまま来日、日本語を習った後、実践に入った秋瑾は、様々な学問や射撃、爆弾の製造法まで勉強した。下田歌子先生とも気があったようだ。清国政府の要請と大陸での利権確保の思惑で、日本国内における革命運動取り締まりが始まると、一斉帰国に反対する魯迅などの他の留学生の前で激高して短刀を振りかざして「死刑」を宣言、1905年に中国に帰った。帰国後は紹興にとどまり、仲間とともに武力による決起を図ったが、計画が途中で露見し清国軍に逮捕され、1907年斬首される。32歳だった。
私がなによりも驚いたのは、紹興の革命記念館で魯迅のすぐ横で見つけた秋瑾の写真だった。中国の清代の女革命家であるからハイカラな洋装か、シナ服かと思いこんでいた。それが和服、しかも実践の昔の制服に短刀というものであった点だ。近寄っていてカメラで、飾られていたこの写真を撮ったのが、『りんどう』に使われている一枚である。秋瑾について描いたものでは、武田泰淳の『秋風秋雨人を愁殺す・秋瑾女士伝』(1968)や山崎厚子『火焔の人・秋瑾』(2007)などがある。また、中国では1980年代に彼女を主題にした映画が制作されているという。もし、紹興にお立ち寄りの節は、革命記念館によってかの国やわが国の志高き人々が政治や未来のことを真剣に考えていた時代に思いをはせてはいかかであろうか。
秋瑾(しゅう・きん)女史のゆかりの地、紹興
<本文>
実践の留学生
秋瑾をたずねて
藤 田 京 子
(昭和一九年卒)
去年の秋、小池邦夫先生主催(絵手紙創始者)の日中友好絵手紙展覧会が中国・上海市の上海芸術院で開かれ、私もへタな絵手紙で参加しました。連日、大勢の人が会場を埋め、たいへんな好評でした。
この旅行の問、私は、ひそかな期待を抱いておりました。それは旅行日程の中に、紹興を訪れる目が組まれていたからです。魯迅の旧居や、記念館を見学するのが目的でしたが、紹興は秋瑾女史の故郷と聞いていたからです。
秋壇女史は、学祖下田歌子先生が、女子留学生として彼女を預かり、その後、秋壇は中国に帰り、清朝末期に、若い女性革命家として、当時の男性社会の中で、救国のために、革命の嵐の中に身をおいて戦い、捕われて、一九〇七年(明治四十年)七月一五日、大衆の面前で処刑されました。「秋雨秋風人を愁殺す」 の句を残して刑死したこの悲しい人、この美しい人は、その時、二十一歳であった。
抗州から、バスでもうもうと上がる黄色の砂ぼこりの中を走ること、二時間、もうそこは紹興の町。道いっぱいの自転車、その間を歩く人の波をかきあげて、警笛を鳴らしながらバスが走りぬけていくと、街の十字路の真ん中に、五、六メートルはあろうかと思われる大きな碑が建っていた。
通訳の女性が「あれは、秋瑾女史という、中国随一の女性革命家の断罪地に建てられた記念碑です」と説明してくれた。
魯迅記念館には、中国近代化のために、革命に殉じた歴代の勇者の写真が飾られてありました。その中でひとりだけ、女性革命家として秋壇が、魯迅の隣に掲示されてありました。 それは中国服ではありません。秋瑾は実践の制服、絣(かすり)の着物に袴姿なのです。私はこみあげる感動でいっぱいになってしまいました。「同じ学校の私が、いま、あなたにお目にかかっております」とつぶやいた時、秋瑾の写真が涙
で見えなくなってしまったのです。
抗州に一泊、翌朝、西湖で、舟に乗ったり、スケッチをしたりした夕方、夕日が湖を茜色に染めるころ、真自な大理石の秋瑾女史の像に会いました。右手に剣を握りしめ、背すじをピソと伸ばし、すくっと立っています。凛々しく、美しい人でありました。その周辺の樹木は、きちんと整備され、秋壇女史に対する中国の人々の思い入れが強く感じられ、こんな立派な人物を教育された下田先生の心意気に改めて考えさせられました。日本語も解せず、日本の習慣にもなれていず、年齢も様々な清国女子留学生を受け入れて教育してきた下田先生。この事業は大正二年まで続き、卒業生は二百余名にのぼるといわれている。またこの留学生の受け入れは、日本の教育史上、実践が一番最初といわれている (明治三十四年)。
実践のみなさん。ぜひご一緒に秋瑾女史に会いに行きませんか。
--平成3(1992)年 実践女子大学国文科会機関誌『りんどう』より
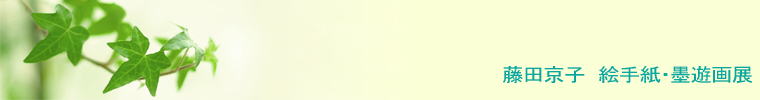

清朝末期の女性革命家 秋瑾(しゅう・きん)女史のふるさとをたずねて
秋瑾の話を最初に聞いたのは、私が実践に在学していた頃。実践女子専門学校、現在の実践女子大学を設立し、私学としていち早く中国から留学生受け入れていた学祖・下田歌子先生のもとで学び、中国に帰って革命運動に殉じた秋瑾(しゅう・きん)という女性がいたという話は、太平洋戦争中で中国との戦争が長引いていたその頃の私には大変、印象深いのもだった。時が流れ、1991年、小池先生からお誘いで絵手紙で中国上海に行くことになった私は、この際、紹興酒の産地として有名な紹興に立ち寄る日程になったいたのを知り、是非秋瑾の縁のある場所に行ってみたいと思った。1991年はこの暮れ、ソビエト社会主義連邦が崩壊して冷戦が終結、中国でも天安門事件のあと停滞していた改革開放政策がやっと勢いを増す、そんな時代であった。下の記事は、帰国の次の年(1992)に、実践女子国文科会の同窓会誌『りんどう』に寄稿した一文である。