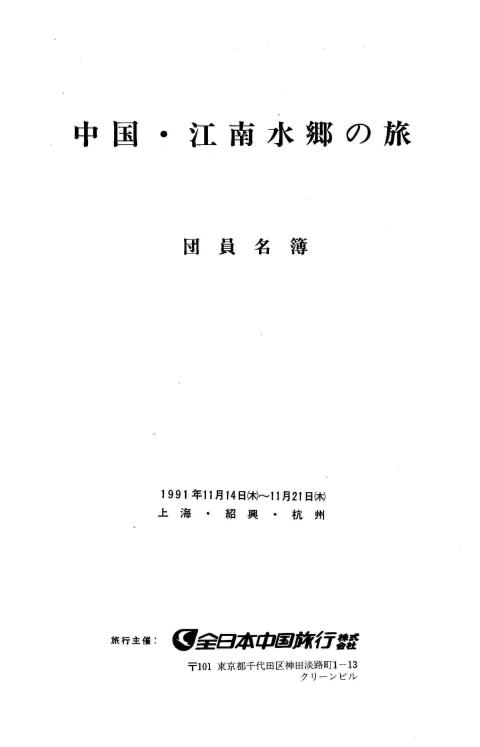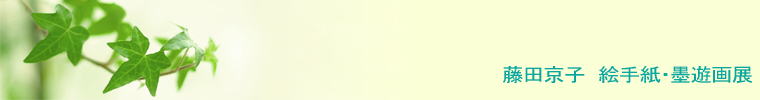開会式を終えての一枚。中央が小池邦夫先生で、その右横が私だ。当時は、今よりかなり、ふくよかだった。
旅行者から参加者に配られた上海交流会の旅行パンフレット。中には参加者全員の顔写真が掲載されている。
上海での絵手紙交流会の会場になった上海美術館の前での記念の一枚。(左から2番目が私)
平成(1989)年
東京国分寺市の光公民館で、小池邦夫先生の「絵手紙講座」を受講する。
この講座は、当時光公民館の中森さんのアレンジによるものだった。
当時、この公民館で「ひまわり会」という油絵のグループに属していて、この公民館に出入りしていた。その何年か前に、個展か展覧会で小池先生の作品をみたことがあり、小池先生のお名前は存じ上げていた。(作品をみたのは、新宿の西口のどこだったか、今では定かではない….本人談。)
6回ほどの講義だったと思う。小池先生は、ご自宅のある狛江から国分寺まで自転車で通ってきた。ある時、雨が降っていたので今日は自転車ではあるまいと思っていたら、雨合羽を着て汗をかきかき自転車で登場。みんな驚いたこともあった。
その後、自主サークルとして光公民館の絵手紙の会も存続。小池先生にはしばらくの間、1年に一度ぐらい来てもらった。
平成3(1991)年
中国・上海市対外文化交流協会の招聘で開かれた上海市での絵手紙交流展に参加
小池先生が招かれたことは知っていたが、中国まで自分が行くとは思っていなかった。そんな折、小池先生から「藤田さんも行こうよ」との電話がある。それまで中国を訪ねたことがなく、ちょうどいい機会だからと参加を決意。この交流会では中国の人たちに、絵手紙を教えるというか、書いてみてもらったが、これは私と旅行に参加した何人かが勝手に墨と筆を持っていて中国の人たちに教える機会があればやってみようという試みで、当初の予定にない行動だった。思った通り中国の人たちは、書や水墨画などにも親しんでいて絵手紙にもすぐ理解を示して、大変好評を博した。そしてこれがきっかけとなって以後、内外で行われる絵手紙交流会でやってきた人たちに対して行われる定番的なイベントになる。
またこの旅行では以前から関心を持っていた清代の女性革命家である秋瑾(しゅう・きん)のゆかりの地である.紹興(しょうこう)に寄ることができ、そこで大変感慨深い思いをした。((詳細はこちら))
上海美術館での開会式のテープカットの瞬間。赤いネクタイが小池邦夫先生
絵手紙を始めてから20年、長いような短いような月日が経った。その間にいろいろなできごとがあった。ここでは、私の絵手紙との年月を、私の師である小池邦夫先生との付き合いを軸にして、まとめてみることにした。小池先生は今や絵手紙をやってみようとする人にとって、知らぬ人はいない絵手紙の第一人者だが、私は今から20年前、東京の西にある小さな公民館での先生と出会うことで、それまで考えられなかった「絵手紙の旅」にでることになった。以下はその軌跡である。
絵手紙との出会い・小池邦夫先生との出会い